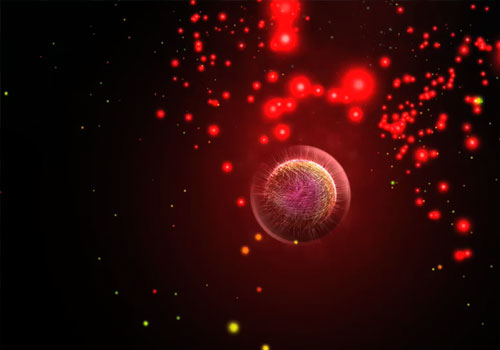Tangible Bitsの誕生は、WIMPがあったから。とくに、P。ポインティングデバイス。
マウスのインタラクションの起源に興味をもって、Doug Engelbartについて調べてみた。
(ネット上にたくさん情報もあるし、『Designing Interaction』にインタビューもある。)
もともと、1軸のホイールだったものを2軸にしたところに発想の転換があったようだが、それよりも、彼が何を考えていたかが面白い 。
『思考のための道具 』より。
「エンゲルバートはヴァネバー・ブッシュのように、人類が解決すべき問題全体の複雑性と緊急性が、社会に培われてきた問題を取り扱う方法を超越するような 時代に突入しつつあることに気がついた。またリックライダーが数年後にわかったように、問題解決における情報の取り扱いという副次的な方法自体が、すべて の問題への鍵 となることが理解できた。最も重要なのはもはや知識の全体量を増加させるための方法を発明することではなく、すでにどこかに見つけられて隠れている答えを つきとめる方法であった。「複雑化した問題を扱う能力を改善できるのなら、人類に著しく貢献できるだろう。それこそ自分の考えていたものではないか。そう して私はそれに手を着けたのだった」」
(自分の人生のゴールについて自問して、時勢に対して自分がどうするかを決めたらしい。かなり、カッコいい!)
複雑なものを扱う手段として、マウスを発明した(これ以外にもいろいろ発明した)、ということなのだと思う。
インターフェイスがいいってことが、人間の能力を拡大したり、人類に貢献できると思うと壮大。
頑張らないと…
Tangible Bitsもそうだけど、やっぱりコンセプト、ビジョンが大事だなぁ。
1962に書かれ、その後、Doug Engelbartがバイブルとしてレポートです。
「Augmenting the Human Intellect:A Conceptual Framewok」1962