物体をさわっているかどうかをわかるらしいです。(笑)
スラッシュドットより
ちょっと、早い4月バカってことでしょうか。
マトリクスLED(BU5004-R)
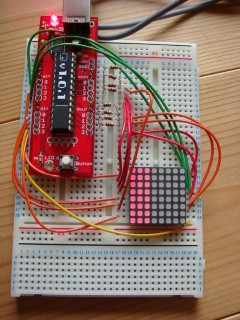
先日、秋月電子で購入。
processing->Gainerでコントロールしようとしたが、どうしてもうまく行かなかった。
上の写真は、Gainerから制御したときの様子。Gainerのmode6で、setHigh()など行うと、列や行単位の制御はできた。
一列のなかをつけたり、消したりということはできなかった。
本来mode7でやるらしいが、processingにはmode7は無い。(みたい)
あえなく、Flash->GSP->Gainerに変更。
画面上でマウスを使って絵を書いて、1フレームづつ保存してアニメーションを作るようなものを制作中。
ちょっと、ペンディングしてるので再開しないと。
Greener Gadgets

今月のWeb Designingに出ていた、
Greener Gadgets Design Competition 2008
のグランプリ作品です。
今使っている電化製品が、どれだけ電気を消費しているかを知ることから
エコライフははじまる、的な作品です。
先日行った「東京工芸大学芸術学部卒業制作展」でも同じような作品があり、
一緒に行った友人と、こういうのあったらいいなー、と話していたところでした。
ただ、その作品は無線管理のために、
それ自体がコンセントにつながれて電気を消費してしまう、
という致命的な欠点を抱えていたのですが、
これはだいぶそういう点でも問題が少なくてすみそうです。
Ishii Hiroshi
会社で石井裕さんの講演のビデオを紹介された。
かなり、グッとくる人だった。
(2歳からPDAをつかっていたらしい。)
Tangible bitsや、作品のいくつかについては知っていたが、何となくロマンチックな印象を抱いていたので、あんなに前のめりな感じだったのは、意外。
(前のめり加減がかなり良いのです。)
と、生き方的にかなりグッと来る一方で、ビデオのなかでTangibleであることの意味を話してたので、ちょっと紹介します。
–
(情報が物理的に知覚できるということは)
Peripheralなawarenessを活用できる
ディスプレイのように集中を強いずに、backgroundの意識で情報処理が可能になる。
過去に培われたKnowledgeが活用できる
モノの形状が、それで何ができるかを伝える
アフォーダンス
Collaborativeな環境をつくることができる
Coincidence of input and output device
入力がキーボードとマウスに限られないので、複数の人がいくつかのモノを操作して
コラボレーションが可能になる。
–
など。
こんなことを意識していたら、ちょっとは役にたつアイディアや、プロトタイプも出来るかもしれない…
いや、できる(はず)。
You tubeにもいくつかあがってたので、リンクしておきます。
プロフェッショナル 石井裕
NHKの番組の時より、講演のビデオの時の方が、グッとくる話をされてました。(ちなみに)
Nintendo DSでシンセ
またまた変化球ですが、KORGのMS-10というシンセサイザーをもとにした世界初のニンテンドーDS専用音楽ソフトが7月に発売されるそうです。ワイヤレス通信で複数台での同時プレイもできるとか。
ちょっとこれは欲しい。
サイトはこちら
嫁が家計簿を付けると言って買ったまま、ほとんど使われていないDSを使うときが来たみたいです。?
FontWeight by processing
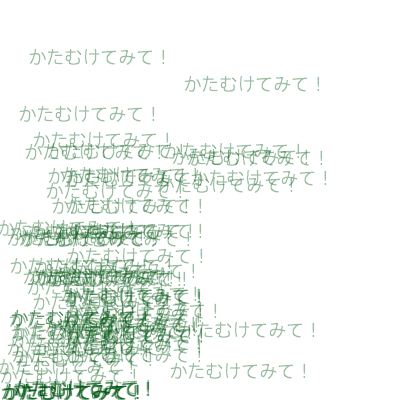
source code:fontweight.pde
Fontをloadして何かしようと思い制作。
ほんとは、fontのウェイトによって、重く見えたり、軽く見えたりしたかったが、今回はウェイト1種類のみ。
AppleSMS(Daniel Shiffman氏のMacBookの加速度センサーから値を取得するライブラリ)と、traer.phisics(パーティクルシステム)のライブラリを使用。
Source Codeのものは、MacBookを傾けると、傾きにあわせて文字が動きます。MacBookじゃないと動きません。
こちらのアプレットのサンプルでは、加速度センサーのかわりに 、マウスの位置を使用しています。
マウスだと、驚きが半減。モノと画面の一致がやっぱり面白い。
生体信号でスイッチON/OFF。バイオスイッチ MCTOS
さっきテレビでやっていたので紹介。
手足や全身の筋肉などが動かなくなってしまった人がコミュニケーションを取れるようにと開発された機械だけれど、とても未来的で感激する。市販されているというのも魅力的。
脳波や眼電信号といった生体信号によってスイッチをON/OFFできるので、テレビ番組では、沈静時の脳波と興奮時の脳波を判別して、クマがシンバルを叩くおもちゃのON/OFFを操作していた。

30:5 by NIN
Nin Inch Nails がghostsというアルバムの収録に使ったと思われるデバイスが、
YouTubeに公開されていました。ピアノとつながっているみたいです。
Voronoi
Voronoi from shiffman on Vimeo.
これ、結構ショック。Daniel Shiffman氏のProcessingの作品です。やっぱり、本物はすごい。
あー、もうボロノイ図が気になってしょうがいない。
もう、がんばってボロノイ図の書き方を理解するしかない。
(physicalネタじゃなくてすいません。ボロノイ図をつかってデバイス入力は面白そう!)
Built with Processing [改訂版]
が間もなく出ると、Amazonさんが教えてくれました。
買ったきりほとんど触っていない人にとっても、
法外な値段で買った人にとっても、
いいんだか、わるいんだか、ですね。